複合文化学科
いま実社会で求められている領域横断的で学際的な視野を身につけるために、目の前にある文化現象(飲食、都市、アート、身体、スポーツ、インターネット、環境、差別など)をさまざまな角度から考察する方法を学びます。
- 取得できる学位
- 学士(学術)
- 取得できる教員免許状
- ドイツ語・フランス語
・中国語・スペイン語
(中学1種・高校1種)
特色
- 1
- 英語以外の外国語力を身につけ、文化や社会に対する複合的な思考を培います。
- 2
- 情報通信ネットワークの技術を習得し、情報を収集・編集して発信する力を養います。
- 3
- さまざまな文化現象を、サブカルチャーから政治/社会現象まで、多面的に分析します。
「遠い場所への想像力」から、「身近な物事の(再)発見」へ、複合的な思考を養います!
この世界はあらゆる文化で満ちています。複合文化学科で学ぶべき文化と出会うためには、「遠い場所への想像力」と「身近な物事の(再)発見」が重要です。
本学科では、英語だけでなく、英語以外の外国語(ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・スペイン語のうち一つ)を専門的に学びます。外国語を学ぶことは、世界の新しい捉え方、未知の思考体系を学ぶことです。外国文学、美術、映画、音楽、社会を学ぶ上でも、他者とのコミュニケーションをはかる上でも、翻訳ではなくその言語を用いることは、異なる文化への根本的な理解のためにきわめて重要なことです。
こうして新たにめぐり会う「遠い場所への想像力」は、逆にこれまで「当たり前」すぎて学問の対象として意識しなかったような、「身近な物事の(再)発見」につながります。例えば日常のなにげない動作・習慣や日本発のサブカルチャー、あるいはすでに海外と国内の文化が融合した、まさに複合的な文化の胎動に気づかされるかもしれません。
本学科ではさまざまな研究アプローチ・方法論を駆使することで、さまざまな文化や社会現象を分析し、考察します。そのためには、情報の的確な収集・整理の技術が欠かせません。
文化、外国語、情報の3つの要素を複合的・有機的に結び合わせ、世界と人間について多面的に考えてゆく──これが複合文化学科の学びのあり方です。

興味範囲の広い人にぴったりの学科です
私は高校生の頃、やりたいことがたくさんあり、学部や学科を絞れませんでした。そんな中で複合文化学科は、一つの学科に所属しながら、文化、情報、言語など広い領域を多面的に学ぶことができる点に魅力を感じました。
1、2年生では、自分の興味を発見するために「複合文化学の建築物」などの入門科目で、さまざまな分野の教授の研究を学びました。これらの授業は、自分が世界をどう解釈するかについて新たな視点を与えてくれ、日常生活で何気なく触れてきたものごとを見直すきっかけを作ってくれました。こうして見つけた関心分野を、3、4年生で深めていきます。現在は英語教育、スペイン語のほか、1年間留学したスウェーデンでの学びをもとにジェンダーやセクシャリティーについて勉強しています。海外に比べると日本ではジェンダーやセクシャリティーに関してはまだまだ保守的な部分があります。卒業研究は海外と日本におけるLGBTQ課題を題材にして進めていくつもりです。
留学や海外旅行の経験から、自国の文化を外国の友達と共有するうれしさを覚えました。また、日本の製品が各国の文化として浸透している現実も知りました。そんなことから将来は、影響力のある日本の製品や技術をもっと世界に広めていくような仕事をしたい、「日本と海外をつなぐ」ような存在になりたいと考えています。
授業紹介
複合文化学テーマ演習
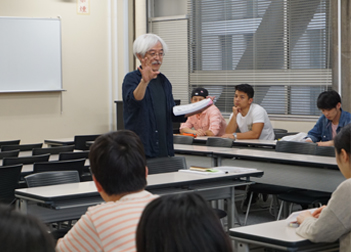
複合文化学科の基幹科目の一つで、1年次春・秋学期にまたがって、複合文化学科全教員によって開講される「基礎ゼミ」です。1クラスの定員を20人以下に抑え、さまざまなテーマをめぐって、研究のイロハを学びます。発表のテクニック、議論のテクニック、論文の書き方のテクニック等々。あくまで学生主体・演習中心の授業であり、3年次以降始まる本格的な卒論ゼミのいわば予行演習のようなものです。
複合文化学の建築物
複合文化学科の基幹科目のひとつで、4つのメニューからなります。「知覚」に焦点をあてる「建築物Ⅰ」、「他者」がテーマの「建築物Ⅱ」、「ハイブリッド」がテーマの「建築物Ⅲ」、「自然」がテーマの「建築物Ⅳ」で、おのおの3 人の複合文化学科教員によるリレー講義です。近代以降、われわれのものの見方・感じ方の前提とされ、自明とみなされる「精神」や「自我」といった文化的枠組をいまいちど検証することが目的です。
社会を未来へと導くフロントライナー 在学生の活躍
森羅万象を面白くしてくれる
小学生の頃に、映画をきっかけにVFX(実写映像とCGなどを組み合わせて架空の映像を作る技術)に強く興味をひかれて、自分でも映像制作を始めた三宅さん。その後独学で技術を勉強し、今では学生ながら映像の分野で目覚ましい活躍ぶりを見せ、今後が大いに期待されるクリエイターの一人となっています。
その活動とは一見関わりが薄いように見える、早稲田大学教育学部複合文化学科に入学した理由、入学して得たもの、そして今後どんなことを学んでいきたいのかを聞きました。
人と人とをつなぐ「共感」というネットワーク
僕は、自分の創作の原動力は「共感」にあると思っています。新しいものを作ることで新たな共感を生むことができる。共感とは人と人とをつなぐネットワークのようなもので、そこには、人に伝える、人に教えてもらう、といった行為が根底にあります。早稲田の教育学部は他の教育学部と少し違って、世の中の物事を自分の力で学び、考え、それを人に伝えることを「教育」と定義しているので、僕の考えている「人とつながる=共感」と、親和性が高いように思えました。中でも複合文化学科は、あらゆる分野を広く深く学べる点で、自分の作り出したい世界観を広げるのに、きっと役立つのではないかと考えて、この学科を選びました。
入学後に履修した中で印象に残っているのが必修科目の「複合文化学科の建築物」という授業です。先生方がオムニバス形式で展開する講義で、建築物といっても建物のことではなく、先生方がこれまで「文化」について考えてきた成果を、「思考の建築物」という言葉で表現しています。ハイカルチャーからサブカルチャーまで幅広く扱うので、自分の活動分野とも重なる部分があって面白かったです。ある意味で早稲田らしいというか、教育の枠にとらわれない授業でしたね。
その後続的な授業である「複合文化学科の組立方」では、神尾教授担当回での「映画館は集合的な夢を見る空間であった」というお話が特に印象的でした。具体的には、映画館は同一の欲望を、同一の時間に、同一の空間で書き込む装置だと言えないか……とする問いかけから始まる、共同体についてのお話で、突き詰めていくと人間の「一つになろうとしながら多様化しようとする」矛盾した性質が見えてくるように感じました。人はなぜ映画を観に行くのか、という自分にとって身近な問いにつながる、非常に面白いテーマの授業でした。
このほか1年次では、一人の先生のもとで、あるテーマについて考察し、発表するテーマ演習もあり、僕の時はジブリ作品を物語や派生作品、背景美術などに区分して話し合いながら分析し、発表しました。2年次では神尾教授が担当されている「複合文化学特論」を受講。精神分析やメディア論などについて、独特な言い回しかつ理解しやすい切り口で学生に問いかける形の講義で、講義後のコメントシートで講義内容について一人で考える時間も楽しいものでした。授業で先生の知見を受け身で流し込むだけでなく、自分で噛み砕いて考えを発展させる作業を毎回やるので、自然と思考をまとめる力がつき、これまで自分の中になかった視点も得られます。
「教育」という言葉の中にある普遍的なもの
複合文化学科は、教員を目指している人は少なく、その分かなりいろいろな人がいます。ゲーム業界に進みたい人や、音楽をつきつめていきたい人、とにかく今を楽しんでいる人。ネットで知り合った人と創作活動をしている人もいれば、歓楽街で働いているという人もいる。文化系寄りのタイプがどうしても多いてすが、あまり方向性は決まっていないですね。自分の知らない世界は世の中にいくらでもあるなとつくづく実感します。知らない世界という意味ではすべて映像制作につながると思っているので、そんな人の話を聞いたりするとお互いに刺激になります。複合文化学科は、いい意味で「必ずしも教員に向いているわけではない人」が集まっているように感じられますし、それがいいところかもしれません。早稲田の教育学部が「教育」を広い意味で捉えているんだなと感じますね。
そういえば接客業でアルバイトをしている友達が、ここで学んだコミュニケーション力が役に立って新しい人とつながったと話していたのが、面白いなと思いました。そういう仕事と「教育」という言葉とは対極にあるかと思いきや、すごくつながりがあった。そういう意味では、普遍的なことを学べる学科ではないでしょうか。
観察すれば、すべての物事が好きになる
CGでバーチャルな世界を作り出す時、そこにリアリティを持たせるには、現実世界に存在するものの細部の観察が必要になってきます。例えば僕は電柱が好きなんですが、一見邪魔なだけに思えても、よくよく見ると技術者の手によって効率的に配線されているのがわかったり、むしろ配線に美しさがあったりします。そういうことは、普段邪魔だなと思って見ているだけだと絶対気づけないんですよね。変圧器とか放熱板の形にも地域によって差があったりするので、関西に旅行した時に、関西電力と東京電力でトランスの形が違うなとか、そういうところがすごく面白く思えてくるんですよ。興味のない人には、それがどうしたの、と言われるかもしれないけれど、それが創作に生きてくるんです。架空の電柱をデザインするという時に、ただ想像で描いてもリアルさは出ない。いろいろ知っていると、電柱の変圧器にはこういう意味があるから、架空のこういう風土だったらこういう形になるだろう、と説得力を持たせることができるんです。
電柱に限らず、観察していくと、すべてのものが好きになります。ちょっとした街の汚れなんかも、一見汚いだけだけれど、複合文化学科的に考えると、こういうストーリーがあって、ここに雨が流れて、ここに錆の跡がついた……そういうバックグラウンドを考えると、すべてに興味がわいてくる。
人間関係にしてもそうで、いろいろなところで働いている人や人の輪を作っている人の話を聞くと面白いなと思うし、自分が知らないところでいろんなことが起きてるんだなと思います。出会った人が、こういう方面に興味があってこういうつながりでこういう業界に行ったとか、そんな話も大好きです。見えている表面だけでなく裏側まで知ると、人間とか文化とかモノとか自然とか、森羅万象が面白く思えてくる。だから何でも興味を持とうと思えば持てる。そしてすべてが創作に結びつく、と感じています。
将来のことはまだ明確に決めてはいませんが、大学にいる間に、文化表象学、メディア論、精神分析といった分野についてより深く学びたいなと思っています。人が織りなす文化やメディアといったテーマは、映像表現の研究に直接つながる部分がありますし、もとより人とそのつながりの中に、映像というものが存在しているのではないかと考えているからです。表現の技術的なことは独学だったり、実際の現場で身につけることができますが、表現する内容は大学での学びのなかで大きく膨らませていけるのではと思っています。
進路状況
自分のこだわり、自分の居場所をみつけるレッスンの場
「文化」「外国語」「情報」——これが複合文化学科の3本柱です。
そして、それら3つの柱をもとに、最終的に「卒業論文」を仕上げることになります。なによりもこの学科の特色は、自分の好きなこと、自分の興味・関心を卒論のテーマにすることができるということです。好きなものほど形にするのは難しい。
しかし、好きなものだからこそ、その人にしか見えないものがある。卒論と向き合う1年間は、いうならば、自分のこだわり、自分の居場所をみつけるレッスンの場といえるでしょう。それはかならずや、みなさんの人生の基礎になるはずです。
2018~2022年度卒業生データ
![教育学科[教育学専攻]教育学専修](./assets/img/modules/sub/ct7/career-graph.svg)