国語国文学科
日本の各時代の文学および言語に関する幅広く多彩な科目と、中国古典の素養・学力を身につける科目が揃っています。国語科教員の養成と、国語国文学の学識の高い、人間味豊かな人材の育成を大きな目的としています。
- 取得できる学位
- 学士(文学)
- 取得できる教員免許状
- 国語(中学1種・高校1種)
特色
- 1
- 国語教育、日本文学、中国文学、日本語学の4つの柱によって、広く学ぶカリキュラム。
- 2
- 高度な専門知識をもつ国語科教員を育てるとともに、日本と世界で活躍する人材を養成。
- 3
- 深く学びたい人のために、各分野における最新の研究成果を取り入れた豊富な授業展開。
文学と言葉を学び、文化について考え、感性を磨き、日本と世界とを往還する視点に立つ
文学も日本語も国語教育も文化です。科学は私たちの望むことなら何でもかなえてくれる可能性を秘めています。しかし、科学が人間の仕事をやってくれるようになったとき、それを受け入れるかを決めるのは文化です。善や悪が地域や時代によって異なるのも、それが文化だからです。
国語国文学科で学ぶことは、文化について学ぶことです。例えば、文学を楽しむことは、多くの場合、文化を受け入れることです。それは文化を支えることですから、とても大切です。しかし、文学について考えることは、多くの場合、文化に違和感を持つことです。これは「問題発見」などと呼ばれています。よく「問題解決型の学習」などと言いますが、それは感性が深く関わる文学を学ぶことによってこそ、より多くの成果を上げることができます。
だから、大学では「自分らしさ」に縛られないでください。それは過去の「自分らしさ」で未来を染め上げてしまうことだからです。変わることを恐れてはいけません。私たち教員も日々変わっています。私たちはすでにわかっていることだけを教えるのではありません。授業は生き物です。学生との対話的な関わりは、学生と教員が協同して優れた国語教員を育てることであり、また企業などさまざまな職場で、そして日本や世界のさまざまな文化のもとで、活躍する人材を育てることでもあります。
国語国文学科はこのような学科です。

幅広い分野が学べる環境が整っています
海外でのホームステイで日本との差異に触れてから、日本文化に興味を持つようになりました。そのような思いから、私は教育学部国語国文学科に進学することを決めました。
本学科では、大学1~3年生を通して、日本の始まりから現代に至るまでの基礎文学史を学び、なおかつ漢文や日本語文法の勉強もします。このように日本文学を全体的に学んだうえで、大学4年生では自分の興味ある分野を研究します。日本文学を幅広く学んでから好きな専門分野に進めるカリキュラムが魅力的でした。また、日本文学では、当時の社会や人間の心理、海外文学との差異などを学ぶことも非常に大切です。その点において、さまざまな学科を有し幅広い講義を受講できる教育学部には、学べる環境が整っていました。
現在、絵本教育について学んでいる私は、卒業後もその知見を活かしたいと思います。しかし、得た知見以上に、さまざまな「表現」を分析するために培ったロジカルシンキングが今後の人生において役に立つのだろうと考えております。
自分の世界が広がっていく体験や、国語国文学科での友人、所属ゼミナールの友人と過ごす時間など、皆さんの大学生活が実りのあるものになることを願っています。
授業紹介
中等国語科インターンシップ
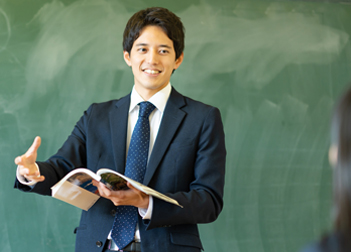
中学校・高等学校の国語科教員を希望する学生を対象にしたインターンシップです。受講する皆さん自身が研究し独自に考案した単元案や自作の教材等をもとに、実際に提携校で授業を行います。事前学習では、受講生同士が協力しながら授業準備や模擬授業を行い、相互評価を経て、実際の授業に臨みます。4年次の教育実習ではできない体験となるでしょう。この授業は多くの卒業生を教育現場に送り出しています。
新国語教育講座
国語の教科書や授業教材に関するオムニバス形式の講義です。国語国文学科の専任教員が1回ずつ、それぞれの専門をもとに講義します。国語教育から日本語学・文学まで、古代から現代まで、日本から中国までを、巡り歩くようにして学び、皆さんが教壇に立った時、生徒にわかりやすく魅力的に教える実践へと結びつけていきます。国語科教員をめざす学生はもちろんのこと、そうではない学生の皆さんにも好評な授業となっています。
進路状況
対話的なかかわりは、活躍する人材を育てることでもある
国語国文学科は、国語国文学の高い学識をそなえた、人間味豊かな中学校・高等学校の国語科教員の養成ならびに社会の多方面において活躍できる人材の育成を目的としています。
卒業生は、中学・高校の教員や図書館司書・博物館学芸員はもとより、新聞・放送・出版などのマスコミ関係をはじめ、一般企業の多種多様な方面で幅広く活躍しています。研究・専門職をめざして、早稲田大学大学院(教育学研究科・文学研究科・日本語教育研究科等)へ進学する者も少なくありません。教育学研究科への推薦入学制度も設けられています。
2018~2022年度卒業生データ
![教育学科[教育学専攻]教育学専修](./assets/img/modules/sub/ct2/career-graph.svg)