理学科生物学専修
生物学・生命科学領域の学識と実験技術を修得し、基礎研究能力を養います。講義で得た知識を展開する実験実習を重視し、研究、教育、産業界で活躍する人材を育成します。卒業生の多くは大学院に進学します。
- 取得できる学位
- 学士(理学)
- 取得できる教員免許状
- 理科(中学1種・高校1種)
特色
- 1
- 分子から生態系まで幅広い視点から生物の成り立ちを理解します。
- 2
- 「顔の見える」教育で基礎から最先端までの理論と実験手法を学びます。
- 3
- 卒業生は研究職や企業、教育などの多様な分野で活躍しています。
ミクロからマクロまで幅広い視点から生物学を学び、自ら探究する力を養う
早稲田大学で初めて生物学を専門とした学科専修として1964年に創設された本専修は、生物学と生命科学の基盤となる知識や研究手法を広く学び、科学的洞察力に秀でた人間を育成しています。
理系学科の中でも実習科目が多いのが特徴で、1年次は物理学実験と化学実験、2年次は基礎生物学実験、3年次は最先端の設備を用いた専門科目の実験実習を履修し、さらに夏季集中授業では軽井沢セミナーハウス、館山・三崎臨海実験所を拠点とした生態学、海洋生物学実習を行っています。 1~3年次は主に早稲田キャンパスで履修し、4年次には大学院生たちとともに、理学、医学、工学の各領域が融合する早稲田大学先端生命医科学センター(TWIns)で卒業研究を行い、卒業すると学士(理学)の学位が授与されます。また所定の課程を修了することにより、理科教員や博物館学芸員等の免許・資格を得ることもできます。将来は、国公立民間研究機関(研究者・技術者)、産業界(医薬創薬、化学、化成品、食品、化粧品、精密機器、情報、出版、シンクタンクなど)、教育界(高等学校・中学校の理科教員、大学教員)、公務員(行政職、技術職)など、様々な場で活躍する人材を養成しています。卒業生の半数以上は大学院(修士・博士)へ進学します。

自分の目で見て触れて考えることを大切に
生物学専修は一学年が40人程度と少なく、実験や実習が多いため、同期と接する機会が多くとても仲良くなれます。全体的にアットホームな雰囲気があり、先輩方や職員の方、教授陣を含めとても優しく、自分が知りたいことやわからないことを丁寧に教えてくださいます。
所属ラボでは、さまざまな生態系における炭素や窒素などの物質循環を理解するための研究を行っています。フィールドワークを基本としていて、実際に森林に行って調査を行います。
私は野外で採取した土壌サンプルを実験室で分析し、土壌と微生物の関わり合いについて研究を行っています。この研究を続けるために大学院に進学する予定です。これからもさまざまなフィールドに出て、自分の目で見て触れて考えることを大切にしていきたいと思います。
授業紹介
生態学・海洋生物学(実習/2~3年生)
「生態学・実習」と「海洋生物学・実習」では生態系の成り立ちや地球上に生息する生物の多様性について学びます。生態学実習では、野外に出て生物集団と環境要因に関する調査を行い、両者の関係について理解を深めます。海洋生物学実習では自ら生物を採集し、発生実験等を通じて生物の多様性の起源を学びます。実習は軽井沢や三崎、館山の森林や海浜を対象とした合宿形式の夏季集中授業を行います。
生物学実験Ⅰ~Ⅷ(3年生)
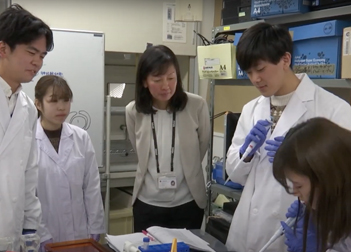
生物学実験I~Ⅷは、講義と結びついた多様な研究課題に取り組み、実践的な研究能力と学識を身につけます。例えば生物学実験Ⅳでは遺伝子組換えヒト増血因子の酵素免疫学的測定法を構築し、超微量生物体分子の定量法を学びます。
進路状況
この半世紀に100名以上の博士(理学)を輩出
大学院進学率が高いのが特徴的で、本専修の卒業生は、教員が兼担する大学院先進理工学研究科へ進学し、修士課程、博士後期課程まで一貫した教育研究システムの中で研鑚を積むことができます。
実際に生物学専修の卒業生の半数以上は大学院へ進学し、この半世紀に100名以上の博士(理学)、400名を超える修士(理学)を輩出しており、研究、企業、教育の各界にて第一線で活躍しています。
2018~2022年度卒業生データ
![教育学科[教育学専攻]教育学専修](./assets/img/modules/sub/ct5_1/career-graph.svg)